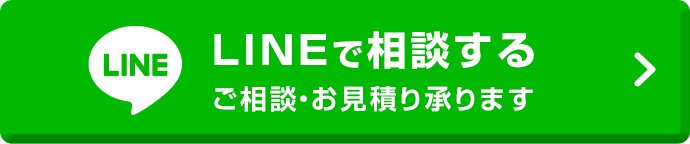蛇の駆除をする際は、まず退治したい蛇が毒を持っているかを確認しましょう。
その蛇が毒を持っているかどうかで駆除方法が変わるからです。
- 業者に連絡する
- 棒でつついて追い出す
- 水をかけて驚かす
- 殺蛇剤で退治する
- 捕獲器で捕まえて遠くへ逃がす
- 放置していなくなるのを待つ
日本で出没する毒蛇は持っている毒が強く、噛まれると命に危険がおよびます。
そのため、毒蛇の駆除は自分では絶対にしないでください。
「あの蛇が毒蛇かどうかわからない……」という方は、害獣駆除110番の利用がおすすめです。
毒蛇でも毒のない蛇でもすぐに駆けつけて駆除いたします。
24時間365日、お電話一本でいつでも駆けつけ可能です。
目の前に蛇がいて不安な方はもちろん、普段から蛇の出没にお悩みの方もぜひご利用ください。
蛇の駆除を自分でできるかの判断基準|危険な蛇の見分け方
日本でよく身近に出没する毒蛇は、以下の3種類です。
- ニホンマムシ
- ハブ
- ヤマカガシ
それぞれの特徴は以下の通りです。
ニホンマムシ

| 体長 |
| 40~80cm |
| 体の特徴 |
| 三角形の頭に体は太く短い 丸の中心に点のついた模様 |
| 生息場所 |
| 北海道~九州 自然の多い場所 |
| 活動時間 |
| 夜 |
ほかの蛇と比べてずんぐりむっくりとしているのがマムシの特徴です。体をぐにゃぐにゃと曲げた体勢をよくしています。
噛まれると出血や血圧低下などの症状が出ますが、死亡率は比較的低く0.1%ほどといわれています。
それでも意識障害やアナフィラキシーショック※1を引き起こすこともあるため、危険ではないというわけではありません。
※1 重篤なアレルギー反応によるショック症状。死に至るケースもある。
参考:重篤副作用疾患別対応マニュアル|厚生労働省
ハブ

| 体長 |
| 100~200cmメートル |
| 体の特徴 |
| 白~黄色の地に黒い網目模様 |
| 生息場所 |
| 沖縄県の22島 |
| 活動時間 |
| 夜 |
沖縄の蛇として有名なハブは大きな個体だと2mを超えます。好戦的なため、絶対に近寄ってはいけません。
人間の体の細胞を破壊する強い毒を持っています。解毒することは可能ですが、対処が遅れると死に至ることもあるほどです。
ヤマカガシ

| 体長 |
| 70~150cm |
| 体の特徴 |
| 丸い顔 体は細長い 赤と黒の斑点 |
| 生息場所 |
| 本州、四国、九州など 森や水辺でよく見かける |
| 活動時間 |
| 昼 |
体の色は住む地域によってさまざまです。
なかには模様を持たない個体や青色の個体もいるので、一目見てヤマカガシと判断することは簡単ではありません。
持っている毒は非常に強く、噛まれたときの死亡率も非常に高いです。
日本に生息する3種類の毒蛇についてご紹介しましたが、毒蛇を見つけたら絶対に近寄ってはいけません。
駆除したい蛇が毒蛇ではなかった場合は自分でも対策が可能です。
詳しい方法については毒のない蛇の駆除方法|追い出し・駆除グッズの使用・放置で解説しています。
自分で見分ける自信のない方は害獣駆除110番までご連絡ください。
プロが迅速に駆けつけて駆除いたします。
※1 対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。※2 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。
安全に毒を持った蛇を退治する方法|蛇駆除のプロに依頼する
駆除しようとしている蛇が毒を持った種類だった場合、対策はプロにまかせてください。
蛇の駆除を自分でできるかの判断基準|危険な蛇の見分け方でご紹介した蛇は、どれも噛まれれば死に至る可能性もあり、非常に危険だからです。
すぐに業者に依頼するようにしてください。
ちなみに蛇が出現した際に警察や自治体に連絡して対応してもらうことをすすめているサイトもなかにはありますが、対応としては正しくないので注意しておきましょう。
害獣駆除110番でも毒蛇の駆除をおこなっています。
毒蛇を安全に駆除するためにもぜひご利用ください。
毒蛇に噛まれてしまったときは病院へ
もし毒蛇に噛まれてしまったら、患部を安静にしてすぐに病院へ行きましょう。※2
間違えても口で毒を吸い出したりはしないでください。
口内に傷があった場合、そこから毒が全身に回ってしまう可能性があります。
タオルなどで患部を軽く縛ったら、すぐに救急車を呼びます。
ためらっていると手遅れになることもあるので、迅速に行動してください。
※2 参考:危険な動植物|厚生労働省
毒のない蛇の駆除方法|追い出し・駆除グッズの使用・放置
駆除したい蛇が毒を持っていない種類だった場合は、対策の難易度はかなり下がります。
しかし、毒がないとはいえ蛇に近づいたりすることに不安を感じる方も多いかもしれません。
この章ではなるべく蛇に近づかないでもすぐにできる、以下の対策をご紹介します。
- 蛇の嫌がることをして追い払う
- 捕獲器や殺蛇スプレーなど駆除グッズを購入してくる
- 安全な場所にいるなら放置する
方法1.蛇の嫌がることをして追い払う

1m以上ある長い棒状のものを用意してください。
その棒で蛇をつつくと、嫌がって逃げていくことがあります。
また、庭であればホースなどで水をかけることも効果的です。
なるべく離れた場所から蛇を攻撃することで、安全に追い払うことができます。
方法2.殺蛇スプレーなど駆除グッズを購入してくる
ホームセンターなどに行けば殺蛇スプレーや捕獲器などの蛇駆除グッズが売っています。
殺蛇スプレーとは、遠距離から安全に蛇を殺すためのスプレー剤です。
そのほかにも蛇を殺すための駆除グッズがそろっている可能性もあるので、一度ホームセンターで体制を立て直してみてもよいでしょう。
インターネットでも購入が可能です。
このほかにも捕獲器を使って捕まえた蛇を遠くへ逃がすという方法もあります。
ただ、屋内などで蛇に遭遇した場合は放置している間にどこかの隙間に入り込んでしまうことも考えられます。
こうした場合は方法1.蛇の嫌がることをして追い払うでご紹介した長い棒を用意するほうがよいでしょう。
方法3.安全な場所にいるなら放置もひとつの選択肢
もし、蛇が生活に支障をきたすような場所にいないのであれば、放置しておくと勝手にいなくなるかもしれません。
庭先や床下などにいる蛇はこの方法が一番安全といえます。
ただし、外にいる蛇が家の中に入ってしまったりすることがないよう、戸締りなどはしっかりしておきましょう。
どうしても蛇が不安なときは害獣駆除110番におまかせください。
退治するのも放置するのも不安という場合は、害獣駆除110番が力になります。
毒のない蛇でも迅速に駆除が可能です。
いつでもご利用ください。
※1 対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。※2 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。
蛇を家に寄せ付けないための対策
蛇が現れたということは、その場所が蛇にとって居心地のいい場所だったのかもしれません。
そのままにしておくと、再度蛇が発生する可能性もあるため、対策を施しておくと安心です。
◆蛇を寄せ付けないための対策一覧
| 対策 | 手軽さ | 効果 | 費用 |
| 臭いを使う | 〇 | 〇 | 500円~1,000円 |
| 隠れ場所なくす | 〇 | △ | 0円~15,000円 |
| エサをなくす | △ | △ | 10,000~200,000円 |
| 隙間をふさぐ | △ | 〇 | 1,000円~ |
できるのであればすべて実行したほうがよいですが、手軽なものだけやっても効果があります。
忌避剤など蛇の嫌いな臭いを使う
蛇用の忌避剤を設置することで蛇を追い払います。
忌避剤はホームセンターやインターネットなどで購入が可能です
ヘビは全身を地面に這わせて移動する動物なので、石や砂など、地面に敷いておくことができるものが効果を発揮しやすいです。
また、わざわざ忌避剤を購入しなくても、タバコを水に浸した液を置いておくのも効果があります。
庭の雑草を刈って隠れ場所をなくす
蛇は暗くて湿ったところを好みます。
そのため、雑草などが茂っていると寄ってくることがあるのです。
蛇が隠れられないよう、余計な草はしっかり手入れして処分しておきましょう。
草刈り110番までご連絡いただければ、蛇が隠れられそうな場所の雑草をしっかり処分します。
ネズミがいるなら駆除する
蛇はネズミを食べます。
そのため、家の中にネズミがいると蛇が餌を求めて家の中に入ってきてしまうことがあるのです。
蛇が侵入する原因をなくすためにも、家にネズミが発生していないか確認して駆除しておくとよいでしょう。
ねずみ110番までご連絡いただければ、ネズミの調査から駆除まで一貫しておまかせいただけます。
>>ねずみ110番の詳細を見る<<
蛇が入れそうな隙間をふさぐ
蛇は体が細く、ちょっとした隙間からも忍び込んできてしまいます。
もし家の周りの塀にひびが入っていたり、屋内に通じる壁に穴が空いていたりする場合はすべてふさいだほうがいいでしょう。
害獣の侵入予防は蛇だけでなく、イタチやアライグマといったそのほかの害獣対策としても有効です。
ただ害獣が入ってきそうな隙間を特定したり、しっかりとふさいだりするのは知識と技術が必要になります。
難しそうと感じたり、作業する時間が取れそうになかったりする方は、プロに任せた方が確実かつラクに害獣の侵入を防げますよ。
まとめ
蛇を駆除するときは、まずその蛇が毒蛇なのかどうかを確認しましょう。
毒蛇であった場合は自分で駆除することは危険なため、蛇駆除のプロに頼るようにしてください。
毒のない蛇であれば自分で駆除することもできます。以下は毒のない蛇の駆除方法一覧です。
- 棒でつついたり水をかけたりして蛇を追い出す
- 捕獲器で捕まえる
- 殺蛇剤で処分するなど駆除グッズを活用する
- 生活に支障がないなら放置する
また、二度と蛇を寄せ付けないよう対策をしておくことも重要です。
自分での蛇駆除や対策について不安がすこしでもあれば、害獣駆除110番におまかせください。
危険が及ばないよう配慮して、安全に蛇を駆除いたします。
24時間365日いつでもお待ちしておりますので、いつでもお電話ください。